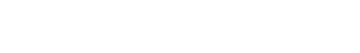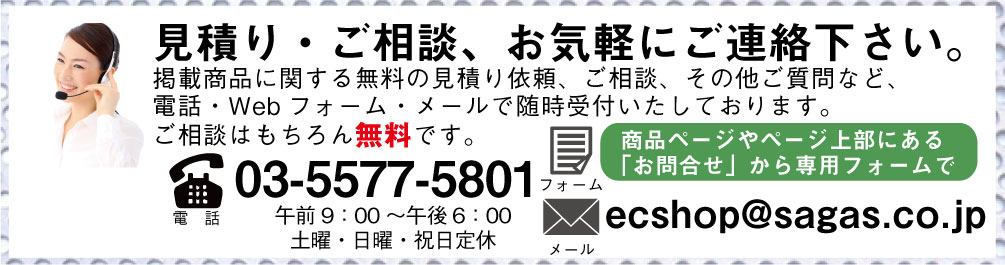役割を取って代わられ、舞台から去るモノたち
2025-02-17
カシオ、電子辞書の開発中止 4〜12月期の純利益57%減(日本経済新聞 電子版より)
平成の初期から中期頃、学校や塾で電子辞書を持っている生徒は、どことなくインテリで裕福なイメージがありました。
ちょっとした偏見でしょうか? みんなが持っていたわけではなかったと記憶していますが、
個人的にはなんとなく憧れを抱いていたことを思い出します。
重くて分厚い辞書を引かなくても、英語や漢字、ことわざや雑学など、知りたい情報が液晶画面に一瞬で表示されるのを見て、
なんだか自分が賢くなったような気分になったものです。
電子辞書は学生だけでなく、海外へ出張するビジネスパーソンや読書家の方々、
さらには一般の社会人でも、スーツのポケットに忍ばせていた人が少なくなかったはずです。
そんな、幅広いユーザー層に一定の需要があった電子辞書ですが、新規開発の終了が発表されました。
あくまでカシオ計算機の発表ですが。
まあ、理由は考えるまでもなく、スマホやタブレットの普及によるものでしょう。
ただ、そもそもスマホやタブレットで漢字や英単語を調べることって、意外と少なくないですか?
辞書を引くという行為は、情報をインプットする作業にあたると思うのですが、
スマホやタブレットの場合、そのまま検索結果をコピーしてアウトプットまで完結できてしまうため、
そもそも「知識として頭に残るのか?」と疑問に思うことがあります。
もちろん、わざわざ言葉を覚えなくてもいいから楽ではあるのですが、
ただ、人と会話をするときに相手から感じる知性って、その人の頭にちゃんと知識があるからこそ生まれるものなのではないかと。
そして、知識が豊富な人との会話は楽しく、話題も広がりやすく、お互いにアウトプットを交換している感覚がある気がします。
ベタな話ですが、自分の頭で考えた言葉とその構成でコミュニケーションを取れることは、
どれだけ電子機器やAIが進化しても変わらない「人の魅力」なのかもしれません。
電子辞書、お疲れ様でした。